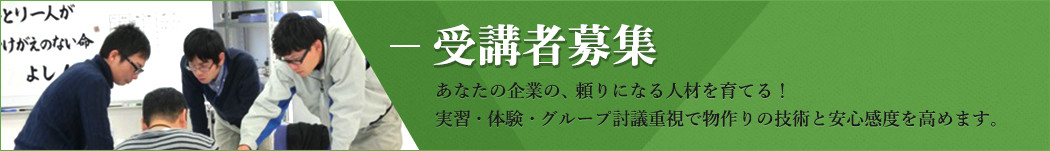講義詳細
安全・安定運転基礎コース(2025年度)
化学工学基礎(リモート)
この講義はリモート講義です
お申し込みの受付を終了致しました。
| 日時 |
|
|---|---|
| 定員 | 20名 |
| 場所 | 地図はこちら |
| 料金 | 72,600円(税込み) |
概要1
科目概要:
流動、伝熟、蒸留に関する化学工学の基礎について学習する。化学工学の原理の基づくプラント運転の基礎を学ぶ。
研修目標(科目全般):
製造現場業務において化学工学の基礎的知識は必須である。大規模なプラント事故が減少し、シャットダウン、スタートアップの機会が少なくなり、体で覚えるというやり方では、安全安定な運転を行うことが難しくなってきた。このような時にこそ、プラント運転の原理を知って、体で覚える運転を補うことが従来にも増して重要になる。
本講座ではプラント運転がどのように行われるのかを理解し、プラントの異常をいち早く感知し、適切な対応が出来る能力を養うことを目標とする。
対象とする研修参加者:
石油化学・石油精製およびその関連産業の従業員
化学プラントの運転に従事する者(オペレーターなど)、設備保全に従事する者(保全技術者など)
科目の特徴:
化学工学は従来、設計者を対象としており、オペレーターのニーズに合うものではなかった。本科目ではオペレーターが必要とする運転のための化学工学を講義する。
一項目毎に、概念の説明、例題の解説、演習の実施と解説、テストと繰り返し学習することで、理解を確実なものにする。
履修者は「APT(運転体験)」を受講すると良い。
プロセス開発、改良、設計を学びたい方は「化学工学通論」を受講すること。
本講座は高圧ガス(化学)資格取得を目指す方にも非常に有効である。
数式、計算が苦手という方にもわかりやすく講義する。
研修に必要な期間:
1時限当たり受講期間:60分~90分
総講義時間18時間半(三日間)+60分テスト
9:00~17:00
受講生数:20名
ティーチング・メソッド:座学と演習
講師:山田知純(山陽技術振興会、元旭化成)
概要2
コマ1:化学工学基礎の基礎(90分) 第一日9:00~10:30
プラント運転、プロセス改良における化学工学の役割を述べ、SI単位系と単位の換算、基礎的な物理概念を修得する。
コマ2:流動(90分+60分)第一日10:45~12:15,13:15~14:45
プラントにおいてもっとも基本的である配管内流動についてその基礎を知る。
現場で出会う流動問題を電卓を用いて解くことで、流動の化学工学的な考え方を身に付ける。
キーワード:乱流と層流、経済流速、粘度、レイノルズ数、
コマ3:流体操作(60分×3)第一日15:00~17:00,第二日 9:00~10:00
ポンプ性能曲線の見方、配管系運転管理の基本的な考え方を修得し、現場操作の原理・原則を知る。
ポンプの吐出圧と流量はポンプ性能と配管特性の両者で決まることを理解する。
ポンプの吐出圧と流量から配管系の異常がわかるようになる。NPSHがわかる。
キーワード:流れの抵抗、摩擦係数、ポンプの性能曲線、ポンプ動力、ヘッド、キャビテーション、NPSH、配管系の運転管理
コマ4:熱移動(60分×2)第二日10:05~11:05、11:15~12:15
化学工学における熱エネルギーの移動の基礎を学習する。特に伝導伝熱と対流伝熱について学ぶ。加熱量、除熱量などの熱量計算ができるようになる。
キーワード熱、熱量、伝導伝熱、フーリエの法則、熱伝導度
コマ5:熱移動操作(70分×2)第二日13:15~14:25,14:30~15:40
化学プラントで多用されている熱交換器の熱移動の原理を学ぶ。熱移動操作の化学工学的な考え方を身につける。
熱交換器の性能はどのようにして知ることができるか?
熱交換器、並流と向流では何が違う?
熱交換器の性能低下にはどう対処する?
キーワード:括伝熱係数
コマ6-1:蒸留(70分+60分×2)第二日15:50~17:00, 第三日9:00~10:00, 10:05~11:05
蒸留の基礎となる気液平衡の基本概念を学ぶ。理想的な場合の気液平衡関係は蒸気圧から求められることを知る。気液平衡の理解が蒸留塔だけでなく、溶液を貯蔵、移動、反応などあらゆるプロセスの理解につながることを知る。
キーワード:蒸気圧、気液平衡、ドルトンの法則、ラウールの法則、相対揮発度
コマ6-2:蒸留(60分+70分×2)第三日11:15~12:15、第三日 13:15~14:25, 14:30~15:40
連続蒸留塔の構造、原理を学び、蒸留操作の化学工学的な考え方を身につける。
蒸留塔の運転操作を化学工学的に解説し、運転のknow-whyを理解する。
還流の意味と役割を学ぶ。
蒸留塔の異常、供給液の変化にどう対処するか、がわかるようになる。
キーワード:多段式蒸留塔、還流、還流比、リボイラー、全縮
テスト:(60分)第三日15:50~16:50
アンケート記入 第三日16:50~17:00
修了証(オンラインの場合は後日郵送)
この講義はリモート講義です
お申し込みの受付を終了致しました。